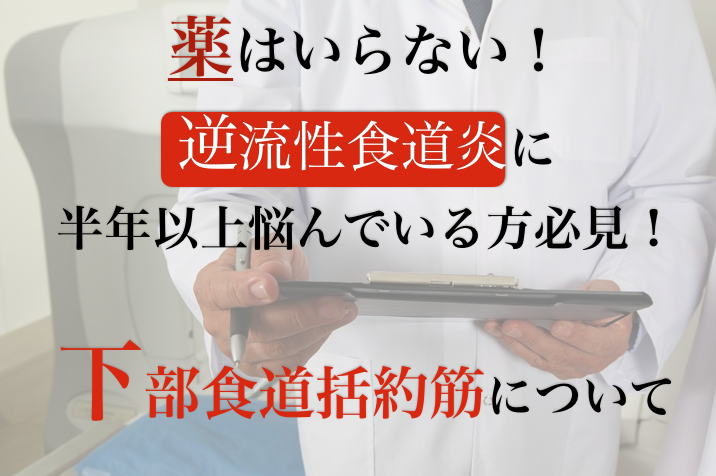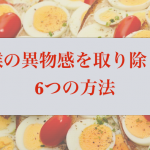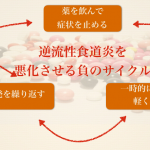3年ほど前から逆流性食道炎を患うようになり、長期に渡る闘病と苦しみの末、なんとかこれを改善したいと色々な治療法を模索し始め、結果完治に至ることができました!
それからは備忘録も兼ね、闘病記として逆流性食道炎に関する様々な項目について書き出しています。

治療方法に関しても、結果の出たものに関しては、私なりに検証結果をまとめています
今回は、逆流性食道炎に非常に関連が深く、逆流性食道炎の根本原因となる食道と胃をつなぐ筋肉(下部食道括約筋)の緩みについてのお話しと、その緩みを改善する方法について、お話ししたいと思います。
「下部食道括約筋を鍛える方法」もたくさん紹介していますので、ご参考になさってみてくださいね。
身近なところからすぐに始められる簡単な実践例ばかりですので、
このページに訪れてくださった方は、少し面倒でも今の苦しみから解放されるために、ぜひ試してみていただければと思います。
腹圧に関して詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
逆流性食道炎が治らないのは腹圧が高いから!腹圧に詳しくなって症状を改善しよう

私は難治性逆流性食道炎の元患者として、今まさに逆流性食道炎に苦しんでいる人に向けて何かできることがある!と感じ、情報を発信しています。
Contents
下部食道括約筋を緩くしてしまう最悪の生活習慣

では、一体どのような生活習慣が、下部食道括約筋を緩くしてしまうのでしょう?
少しだけ、私自身のお話をさせてください。私が逆流性食道炎を発症したのは47歳の頃でしたが、病気になるかならないかくらいの頃の、当時の自覚症状としては、加齢のためか動くことがだるくなり、全身の倦怠感や疲れも慢性的に感じているような状態でした。
子育てがひと段落して夫婦の時間も増え、一緒にお酒を嗜む時間が増えたりもする一方で、おそらくは子どもが巣立ってこれまでとは違う夫婦関係になったことや、仕事上(50歳になる今でも、簡単なデスクワークを行っています)におけるストレスも溜まっていたのか、たまにストレス発散で過食気味になってしまうことがありました。
また、若い頃からの勤務前の習慣で、コーヒーを飲むのが大好きで、朝起きて一杯のコーヒー、仕事前に一杯、休憩中に、ランチタイムに、夕方の休憩中に、帰宅後夕食の後に……と、一日数杯のコーヒーを飲んでいました。
気づけばお腹周りに若い頃にはなかったお肉がついていました。主人が脂っこいものが好きなので、主人の好みに合わせた家での食事が脂っこいメニューになりがちだったこともあるかもしれません。
少しでもスタイルよく見せたくて、パンツスタイルの時は体を締め付けるような服を着て、ベルトも少しきつめに通してみたり。もともと猫背気味だったものが、さらにお腹のお肉も気になって、隠したくてより猫背気味になってしまったり……。と、
振り返れば、まあ体に良くないことのオンパレード、といったような生活を送っていました。
昼食後や夕食後は眠気に逆らえず、特に家では横になって休んでしまうこともありましたね。
そしてなんと、結果的にはこれらのすべてが、逆流性食道炎の原因になっていたのです!
- 運動不足
- 全身のコリ
- お酒を飲む習慣
- ストレス
- 過食傾向
- コーヒー(カフェイン)の継続的な、少なからぬ量の摂
- 脂っこい食事
- 体を締め付けること
- 猫背になりがちな姿勢
- 食後すぐに横になって休むこと
 マツモト先生
マツモト先生これらすべてが逆流性食道炎や下部食道括約筋に対しては良くなかったということですね。
下部食道括約筋に優しい生活習慣

私は、これらの生活習慣から少しづつ見直し、正すことにしました。
具体的には、
- 運動や入浴、寝る前のストレッチなどを基本に、たまの整骨院やカイロプラクティック、整体などで全身のこりをほぐすことに努める
- お酒を飲む量を徐々に減らしていき、こまめな休肝日を設けたり、隔日にすることからはじめる。やがてほぼやめる状態に近づける
- 下記で紹介するトレーニング等により、ストレスの解消に努める
- 食事の時は腹8分目を心がける
- コーヒーもお酒と同様、朝と夜のみ、疲れたお茶の時間のみ、など1日の摂取量を減らしていきました。今では1日一杯程度です。
- 脂っこい食事メニューを改善し、質素めでシンプルな食生活を心がける
- ゆとりのある服を来て、腹部を締め付けるような服装はやめる
- 気がついた時に背筋などの姿勢を正す、下記のストレッチや運動で体幹を鍛え、姿勢の基礎を整える
- 食後すぐに横になることはしない
(※カイロプラクティックや整体で逆流性食道炎そのものに対する効果はあまり感じられませんでしたが、体のこりなどは治療中・治療直後はいくぶん楽になりました))
(※病気が徐々によくなっていくにつれて、ストレスそのもの自体もなくなっていきました!)
なかには当たり前のように感じられることもありますが、こういったひとつひとつの積み重ねが、私の病を完治の方向まで導いていったのですね。

「当サイト管理者(50歳女)が逆流性食道炎を発症させたきっかけと苦しいまでの症例」私の体験談をご覧ください
具体的に実践!下部食道括約筋を鍛える方法

それでは、お待ちかね、下部食道括約筋を鍛える方法について見ていきましょう。
- 呼吸法に関するもの
- 日常に取り入れられる軽い運動
- 筋肉を鍛えるトレーニング
この3つがあります。
■呼吸法に関するもの
呼吸法に関するトレーニングのメニューは、以下です。
- 腹式呼吸法
いわずとしれた腹式呼吸ですが、効果は絶大です。
やり方としては、立位の場合、
- 背筋を伸ばして、鼻からゆっくりと息を吸い込むようにし、お腹に空気を入れるイメージで膨らませていきます
- 次はお腹を徐々にへこませていくようなイメージで、口からゆっくりと息を吐き出します。
時間は、息を吸い込んだ時と同じくらいにゆっくりと。
物理的に手で触れてみるのでも、ご自身の意識を腹部に向けてみるのでも、どちらでも大丈夫なので、「お腹の筋肉を動かしていること」に意識を傾けて実践してみましょう。
- 寝た体勢で実行する腹式呼吸法
こちらは、上記の腹式呼吸法の横になって行うバージョンで、もう少しトレーニング要素が強いものになります。
- ご家庭にある、凍らせていないアイスノン(氷枕)か通常の枕とタオルなど、固くなくお腹にフィットしやすいもので、500g〜1kg程度の重りを用意します
- 仰向けに横になります。両膝を立て、両腕を軽く開き、手のひらは上に向けるようにします。こうすることで、肩や胸を開くことができ、よりリラックスできる姿勢になります。
- お腹の重りを持ち上げるようにイメージしながら、鼻からゆっくりと息を吸い込みます
- お腹で重りの重さを感じながら、それを受け止めるようにしてゆっくり鼻から息を吐き、脱力します
(※トレーニングを始めたての際など、手による体重の支えが必要となる場合には、手のひらの向きを返して床に当て、体重を支えられる体勢を図りましょう。また、両膝を立てることにもリラックス効果がありますが、トレーニング初期に緊張があった方がやりやすい場合は、両膝を伸ばした状態でも大丈夫です。)
自分の中で重りが持ち上がりきったと思えるくらい吸いきったら、そのままの体勢で10秒間キープします。力みすぎて体の他の部分に力が入らないよう、注意しながら行いましょう。
(※腹式呼吸時と異なり、「鼻から吸って鼻から吐き出す」という呼吸法式を取ります。ただし、息を吐く時に苦しさを感じる場合は、口と鼻の双方を使っても構いません。)
以上の1〜4の動作を、一回5〜10呼吸分行います。この1セットを週に3〜4回行うようにしましょう。
一度に長時間行うと、体に過酸素摂取状態を起こし、逆に体調が悪くなることがありますので、注意して行ってください。
- 鼻呼吸法
字に書かれたそのままですが、日常生活において、「口からでなく、鼻から呼吸することを心がける」ということです。
それだけのものすごく簡単なことなのですが、鼻呼吸の方が脂肪が燃焼されやすいというデータもあるので、ダイエットを考えたい人には一石二鳥です。
また、姿勢をシャンとして呼吸することを心がけるだけで、一回あたりに吸うことのできる空気の量が増えます。これはあらゆる呼吸法に適応できます。
- ドギーブレス法
これは犬の呼吸を真似る発声練習法の一つでもあり、腹式呼吸のコツを得られる効果もあります。
- 口をぽかんと開け、リラックスさせるようにします
- イヌが暑い時などに連続して息をつくように、「ハッ、ハッ、ハッ、ハッ、」と小刻みな呼吸を繰り返します
- この1〜2を15秒〜1分くらい続けます。これを1セットとして、1日に2〜5セット行う
小さく吸って小さく吐くように、「ハッ」の発音を心がけましょう。その際にみぞおちの当たりに手を当てると、呼吸に合わせて細かく震えているのがわかるかと思います。
応用編として、
•同じ要領で、「ハッ」という音の代わりに母音「あ、い、う、え、お」を短く発声する
•同じ要領で、今度は「あー、いー、うー、えー、おー」と長母音的に発声する
という、声量のトレーニングもあります。
- 丹田呼吸法
お腹にある「丹田」というツボを意識した呼吸法です。おへその部分から、指を横向きにおいて約2.5本分下方にあります。
- まず、体内のすべての空気を吐き出します
- お腹に向かって、息をゆっくりと吸い込みます。この時、足先から頭に向けて空気が渡ってきているイメージを持ちましょう
- 口を閉じ、前歯の裏にしっかりと舌を付けます
- 息を止めます。先ほどのイメージの中で頭に渡っていった空気を、今度は頭から丹田まで下ろしていくようなイメージを持ちます
- 10秒間かけて、止めていた空気を吐き出します
- ヨガ呼吸法
- まず、しっかりと背骨を伸ばします。徐々に肩の筋肉の力を抜いていき、ゆっくりとリラックスさせます。その後、目を閉じます
- 肺を大きく膨らませるイメージで呼吸します。このとき、背骨や首がきちんとまっすぐになっているように意識しましょう
- 「吐く・吸う」の動作を、テンポよく繰り返します
この1〜3 を繰り返します。このとき、リラックスできるたとえば自然空間にいるときのようなイメージで行いましょう。
新鮮で美味しい空気を体内に取り入れるようなイメージです。
心と体のリラクゼーション効果を得ることができます。
この、「丹田呼吸法」と「ヨガ呼吸法」、そして最初の「腹式呼吸法」に関しては、「逆流性食道炎の悪化予防!私がオススメする3つ呼吸法をランキング形式でお伝え!」
でもより詳しく動画付きで私なりに紹介していますので、よろしければご覧になってみてくださいね。
- システマ呼吸法
- 背筋を伸ばします
- 鼻から息を吸います
- 口をすぼめて息を吐きます
この1〜3の動作を繰り返します。かつては昔のソ連軍の訓練方法の一つでもあったらしく、「どんな状況でも平常心を保つこと」を目的に開発された呼吸法なので、精神のリラックスやコントロールに非常に有効な呼吸法です。
また、少し派生したバージョンで、歌を歌う時のボイストレーニングに起因したものもあります。
- ロングブレストレーニング
- 立った状態か座った状態、どちらかやりやすい法を選択します。その状態で、息を鼻から、「限界!」と思うまで吸い込みきります
- 吸った時にかけた時間の倍以上の時間をかけて、口からゆっくりと息を吐きます。(※この時、上で説明した「腹式呼吸」を心がけましょう
これを1日30回程度を目処に行うトレーニングです。
- ブルブルトレーニング(※ビブラートのイメージを体感で掴む練習法です)
やりかたは以下です。
- まず、背もたれのある椅子に、リラックスした状態で腰掛けます
- 肋骨のすぐ下当たりに、にぎりこぶしを作ってグーの状態にした両手を当てます。「あ」の発音をするときと同じように口を開けます
- 息を吸います
- そのまま、「あー」と伸ばすようにして発音し続けます
- 発音を継続したまま、肋骨の下にセットした両手で小刻みに腹部を軽く刺激します
ゆっくりとした一定のリズムで「ブルブル」と押していくようにすると、「あーあーあーあー」といったように発生中にビブラート音がかかるようになってきます。
慣れてくると立っている状態でも動作が可能になり、さらにもっと慣れてくると、手を使わなくてもいつの間にかできるようになっています。
- スタッカート式呼吸法
短く切って呼吸を繰り返す呼吸法です。主に吐く時のリズムを心がけます。
「スーッ」と長時間かけて息を吐くのではなく、イメージとしては「スッ」という短い瞬間で息を吐き切ります。
ピアノなど楽器をやっている方はわかるかと思うのですが、本当に短い瞬間で、シャープな音を繰り返すのが「スタッカート」です。「スッ、スッ、スッ、スッ、スッ、……」というリズムを意識して行いましょう。
体感としての力の入れどころとしては、腹筋、背筋、体の側面の筋肉のそれぞれに、息を吐く瞬間だけ一瞬力を、その後素早く脱力します。細切れに息を切るようにして行なうイメージです。
- 瞬発筋を鍛えるトレーニング
- 足を肩幅に開いて立ちます
- 手を両脇腹にあてます。その後前屈し、体の曲がる角度が90度近くになるよう、徐々に前に体を倒していきます
- 2の体勢で体を止め、口を閉じます
- 鼻からの呼吸で、ゆっくりと限界まで息を吸い込ます
- 再び鼻から、今度はゆっくりと限界まで息を吐ききります
- 1〜5の実践を繰り返すのですが、行っていく際にだんだんとスピードを上げていきます。限界だと感じるスピードまで速度をあげたら、その後はそのスピードで継続させてトレーニングを行います
- 持続筋を鍛えるトレーニング
- 足を肩幅に開いて立ち、手を腰に当てます
- 深呼吸を2回繰り返します
- 3度目で、もう一度息を限界まで吸い込みます。そうしたら、前歯を閉じ、その内側に舌を当て、「ツー」という発音で発声します。
- 発声にムラが出ないよう、一定の音量を持続するように心がけながら、発声を続けます
- 限界まで息を吐ききったら、突然ではなく徐々に音を小さくし、フェードアウトさせるように音を消していきます
ゆっくりと、限界まで息を吸い込み、その後すべての息を吐き出すように心がけましょう。
(※場を鎮める時に人差し指を立てて「しーっ」と言う時の、前歯が閉じられていてその裏に舌が付いているバージョンです。息が漏れるような発声を心がけましょう。)
この最後の部分が、頭に血がのぼるくらい息を吐き切ることにつながるので、やってみると結構キツイです。
以上、ボイストレーニングから適用できる実践はいかがでしたか?
実は、歌を歌うこと、それ自体でも、下部食道括約筋やその周囲の筋肉を鍛えることに繋がるんですよ。
日常の合間、歌えるタイミングがあったらどんどん歌ってしまいましょう!
日常に取り入れられる軽い運動
続いて、日常に取り入れられるライトな運動のご紹介です!
- ウォーキング
ウォーキングはウォーキングでも、一つ上の項でお話しした「腹式呼吸」を行いながらのウォーキングが、逆流性食道炎の治療時には最も効果的です。
ただし、食後すぐのウォーキングは、消化に集中している胃に集った血液を分散させてしまい、胃や消化器官にかかる負担を大幅に増やしたり、消化不良につながったりと、本末転倒です。
食後1時間以上の時間を空けて、お食事の消化がある程度落ち着いた頃に行うようにしましょう。
- ドローイン
- 床の上に横になります
- 仰向けになった状態で、両膝を立て、膝の力を抜いてリラックスします
- 鼻から息を吸って、お腹をできるだけ膨らませるようにします
- 口から大きく息を吐きます
楽な体勢を取るように心がけてください
その際にお腹をできるだけ大きくへこませるように心がけます.
以上の4つの順序を繰り返します。。
このトレーニングはだいぶ効果がありますが、ウォーキング同様、腹部に結構な負担をかけることになります。食後すぐなどのタイミング避けて行いましょう。
- ティッシュを使った運動
身近なアイテム、ティッシュでも、腹部の筋肉を鍛えることが可能です。
- ティッシュを2~3枚取り出します。その後、それを丸めて口に挟みます
- その状態で、ゆっくりと時間をかけて、限界まで息います
- それから、「うー」と低い声を発しながら、吸い込んだ息を吐き切ります
 ナース
ナースたったこれだけですが、効果はかなりありますよ
これだけです。
- 横隔膜のストレッチ
立った姿勢、座った姿勢どちらでも実践可能です。やりやすい方で試してみましょう。
- まず、腹式呼吸で呼吸を整えます
- ゆっくりと口から息を吐きます
- ゆっくりと体を前に倒し終わったら、今度はゆっくり鼻から息を吸い込むようにして、そのままのペースで上半身を元に戻します
- これら上記1〜3の運動を、4、5回繰り返します
そのまま前へお辞儀をするように上半身を倒していきます。イメージとしては、体を前へ倒しながら、同時にお腹から空気を抜きつつ息を吐くような感じです。
このときのイメージは、お腹に空気を入れて膨らませる感覚です。
以上、1〜4で1セットです。
この運動を、目安としては一日3回。朝目覚めたあとと、日常生活の合間に取り入れ、行うのが良いでしょう。
筋肉を鍛えるトレーニング
最後は、だいぶかっつりしたトレーニングになります。
- サーキットトレーニング
サーキットトレーニングとは、複数の筋肉トレーニングを順番に組み合わせて行っていく、「体系立った筋トレ」です。
たとえばの例ですと、
- 腕立て伏せ20回
- 腹筋20回
- スクワット20回
- 背筋20回
この1〜4を1セットにして行なうようにします。メニューとしてはまあまあハードなものになりますが、お家でも実践できる、場所を選ばない手軽さがあります。
あまりに普段運動されない方でしたら、それぞれの回数を半分の10回に減らしてもいいかと思います。
また、トレーニングの途中で呼吸を整えることも大切で、1セットやったら呼吸を整え、続いての1セットをやったら再び呼吸を整えて、…といったような繰り返しが大事です。
理想は、1日15分以内の取り組みを心がけてください。それ以上の実際は、肉体的な損壊を引き起こしがちです。
本来のサーキットトレーニングはさらに複数の筋肉トレーニングを組み合わせて行われることが多いですが、今回は本来の目的から少し離れて、逆流性食道炎をの治療を目的としているので、上記に書いた「腕立て、腹筋、スクワット、背筋」の実践だけでも効果が出るかと思います。

この中でも、一番優先順位が高いのは「スクワット」。私も最初は、これからはじめました(残りの4つも、あまりまめにはできず、回数もできたものでもずっと10回のままだったように記憶しております…(笑))
4つのメニューをこなせない場合は、まずはスクワットからだけでも試してみると良いでしょう。
以上、たくさんのメニューを見てきましたが、ご自身で実践できそうなものはありましたか?
もちろん、すべてを試さなくて良いので、この中からでもご自身でできそうなものを選んで、まず最初はだいぶ少ない回数を隔日でこなすところからでも、やんわりと日常生活に取り込んでいってみてくださいね!
いずれ癖がつき、習慣になったら早いですよ。
私は難治性逆流性食道炎の元患者として、今まさに逆流性食道炎に苦しんでいる人に向けて何かできることがある!と感じ、情報を発信しています。
マツモト先生のサイトと出会い、マツモト先生のメルマガを通じて逆流性食道炎が良くなり、私は心も体も元気になりました。
その考えを普及したいと思い、サイトを立ち上げました。
マツモト先生から許可をいただき、私のサイトからもメルマガ登録できるようになったのでメルマガ登録することをオススメします。
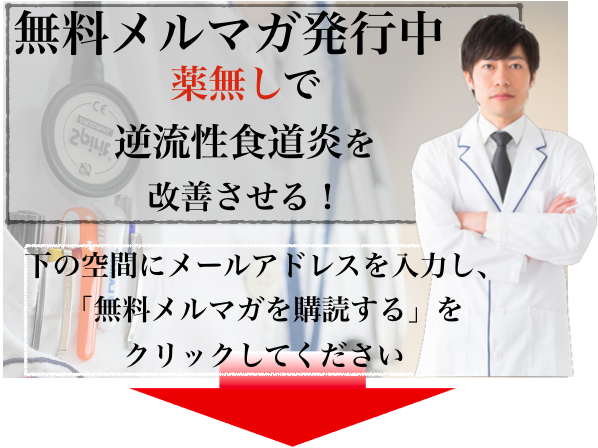 |